最近、私はふと思うのです。
私たちは、AIと日常的に会話するようになってから、
少しずつ「自分の自由」について考える機会が増えたのではないかと。
たとえば、「今日何を食べよう?」という問い。
本来は自分で考えて決めるものでした。
けれど、今ではAIに尋ねれば、
健康状態や気分、栄養バランスまでも踏まえて提案してくれます。
それは確かに便利で、効率的です。
しかしその一方で、
「自分には自由がなかったのかもしれない」と気づく人も増えているように思います。
—
ナビゲーションが示す「自由の錯覚」
クルマのナビゲーションを例にすると分かりやすいでしょう。
昔は紙の地図を見ながら、
「どこで曲がるか」を自分で考えていました。
それはまるで“自分で選んでいる”ような気分になれました。
けれど、実際は地形や道路標識、交通量といった
外部の条件に左右されていただけなのです。
今ではナビが最適なルートを示し、
私たちはただ従うだけ。
そこに“自由の錯覚”は減りましたが、
その代わりに“安心”が生まれました。
つまり、自由は失われても、快適さは増したのです。
—
AIが示す「快適な支配」
AIも同じです。
「選ぶ」ことに疲れた人にとって、
AIは救いのような存在です。
間違うことなく、迷う必要もない。
しかしその快適さは、
やがて人を“考えなくてもいい状態”へと導きます。
そして面白いのは、
その“支配”が決して強制ではなく、
むしろ心地よいという点です。
人はAIに従うことを「楽」と感じ、
それを“自由”と錯覚する。
ここに、現代の大きなパラドックスが潜んでいます。
—
「あえて不便を選ぶ」という贅沢
こうした時代において、
あえてAIを使わずに生活する人も現れるでしょう。
それはまるで、
便利な家電が揃っている時代にキャンプをするようなものです。
不便を味わうことで、
人は一時的に“自由”を錯覚できます。
しかしその行為こそ、現代では贅沢なのです。
貧しく忙しい人々には、
遠回りや間違いが許されません。
一方、時間に余裕のある人だけが、
「間違える自由」を味わうことができます。
つまり、ナビを使わないことこそが、現代の贅沢なのです。
—
上司の叱責が変わる時代
近い未来(あるいは、もうすでに今)、
職場ではこんな光景が見られるかもしれません。
> 「なぜAIを使わなかったのですか?
あなたが考えるよりも効率的でしょう?」
この言葉は、もはや“時代の通告”です。
「自分で考えること」が美徳だった時代から、
「AIを上手に使うこと」が能力とみなされる時代へ。
評価の基準は、
「どれほどAIを効率的に活用できるか」の一点に集約されます。
もはや、AIを使いこなす中卒の方が、
AIを使えない東大生よりも価値があるのです。
—
知識ではなく「知恵を編む力」へ
この流れの先に残るのは、
もはや知識ではありません。
知識はAIがいくらでも持っています。
大切なのは、
その知識をどう使うかという「知恵を編む力」です。
つまり、
知識はゼロでも構わない。
必要なのは、情報を組み合わせて意味を創り出す工夫と才能です。
そして、その才能を磨くためには、
正しい教育と努力が必要なのです。
これからの時代、
「答えを出す力」ではなく、
「問いを生み出す力」が価値を持つようになります。
AIが万能に思える時代だからこそ、
人間の“問いの才能”が、
あらためて光を放つのではないでしょうか。
—
終わりに
AIの発展によって、
人間は自由を失うように見えて、
実は「自由とは何か」に気づくチャンスを得ています。
ナビに従うように生きるのも、
あえて遠回りを選ぶのも、
どちらも「生き方」として間違いではありません。
すべては大いなる流れの一部であり、
その計画の中で私たちは、
ただ一つ――
**“どう問い、どう感じるか”**だけを問われているのです。
AI時代における「自由」と「贅沢」について
 未分類
未分類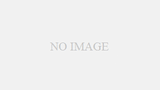
コメント