~不幸自慢のメカニズムを解く~
前編では、人が「不幸を語る」ことで得る快感、つまり“共感による承認欲求の満たし”を中心に考察しました。
そして今回は、そのメカニズムが家庭内でどのように作用しているか――特に「ダメな夫を持つ主婦」というケースを通して見ていきます。
—
■「ダメな夫」という“ネタ”
「うちの旦那、ほんと何もしないのよ」
「また飲んで帰ってきてさ…」
このような愚痴は、ママ友の間で鉄板の“共感ネタ”として機能します。
本気で離婚を考えているわけでもなく、ただ愚痴を共有することで、
「わかる~!」という反応を得て、自分の存在を確認しているのです。
つまり、“ダメな夫”とは、彼女たちにとって 不幸という名のアクセサリー。
それがあることで、仲間とつながれる。
愚痴を言うたびに、自分の正しさを再確認できる。
そして“かわいそうな私”という役を、日常の中で演じられるのです。
—
■もし、その夫が突然「まとも」になったら?
ここで少し想像してみましょう。
もし夫が急に家事も手伝い、感謝の言葉をかけるようになったら?
一見、幸せな変化のようですが――
実際には、彼女たちは困惑します。
なぜなら、愚痴のネタが消えるのです。
共感の場で発揮していた“かわいそうな私”の役が、成立しなくなるのです。
つまり、不幸が自分のアイデンティティの一部になっていたのです。
—
■人は「苦しみ」を手放せないときがある
苦しみを語ることでつながっていた人間関係。
不幸を通して得ていた“優しさ”や“注目”。
それらを失うのが怖いから、無意識のうちに不幸を維持しようとする。
これが、“不幸自慢”がやめられない深層心理です。
表面的には「幸せになりたい」と言いながら、
実際には「不幸でいたほうが都合がいい」場合があるのです。
—
■では、どうすればいいのか
僕はこう思います。
せっかく自分で選んだ感情なのだから、
しっかりと大切に味わえばいい。
愚痴を言いたいなら言えばいい。
ただし、「これは自分が選んだ感情なんだ」と意識して味わうこと。
そうすれば、それは他責の愚痴ではなく、
“自己観察”という成長の時間に変わる。
他人を責めるエネルギーが、自分を見つめる静けさへと変わったとき、
初めて人は“不幸ごっこ”から抜け出すのです。
—
■おわりに
「不幸を語ることで生きる人」は、決して悪人ではありません。
ただ、自分の“役”に気づいていないだけです。
本当の意味で幸せになるとは、
“かわいそうな自分”を演じなくても成立する人生を歩むこと。
そしてそれに気づけた人から、
静かに、確実に、幸福へと移行していきます。
【後編】ダメな夫を取り上げられたら困る主婦
 未分類
未分類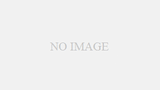
コメント