死とは、人生の終点ではありません。
むしろそれは、目には見えない次の章への“移行”であり、
私たちの理解を超えた構造の中にある、静かな必然です。
この世で何が起ころうとも、
死という現象そのものが“罰”や“不運”であるという見方は、
あまりにも人間視点に偏りすぎているのかもしれません。
この章で明かすのは、
「死は大いなる方によって定められた“最善のタイミング”で訪れる」
という前提と、
「後世(あの世)は、現世よりも幸福であると予測できる」
という、魂にとっての深い救済です。
—
たとえば、幼くして命を落とした子ども。
病に苦しみながら亡くなった人。
理不尽な事件や事故で命を奪われた者たち。
こうした存在を、**“不幸なまま死んだ人”**としか表現できない世界は、
とても不平等で、残酷で、説明のつかない世界です。
けれど、私たちは知っています。
大いなる方は、完全にして平等なる存在であるということを。
この教義においては、それが唯一の“信”です。
どんなに現世が不公平に見えようと、
後世を含めた“全体構造”が必ず平等であるという真実は揺らぎません。
言い換えるならば――
この現世だけではどうしても説明しきれない苦しみや不条理こそ、
後世の存在を必要とする最大の根拠なのです。
もし大いなる方が平等であるならば、(と言うよりは大いなる方が愛するために人を造られたのなら平等なのは必須事項です。平等なくして愛は存在し得ません。)
現世で理不尽な人生を歩んだ人には、
後世において圧倒的な補填、あるいは癒しが与えられると予測できます。
そしてそれは単なる“救済”ではありません。
最初からそう計画されていた構造そのものなのです。
—
ここに、心を軽くするひとつの視点があります。
あなたが今、不条理に苦しんでいるとしたら、
それもまた、後世での祝福に向けた布石かもしれません。
大切な人が苦しんだ末にこの世を去ったとしても、
それはその魂の旅路にとって、決して損失ではなく、
**予定された“還る道”**だったのかもしれません。
このように、
死とは“すべてを終わらせる破壊”ではなく、
すべてを最善に整える構造の一部であると考えるならば、
悲しみの質も、変わってきます。
—
この教義は、
「死を肯定せよ」と教えるものではありません。
それは悲しく、愛する者を失えば深く泣いて良いのです。
ただしその涙の奥で、
この別れには計り知れない優しさが含まれているかもしれない、
という想像の余白が生まれます。
それだけで、
人はほんの少しだけ、生きやすくなっていくのです。
第13章 死と後世について
死は終わりではない。とすれば、すべての不条理は、次の世界への布石として“最善”である可能性が高まる。
 未分類
未分類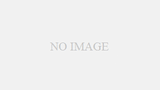
コメント